━━「夜を賭けて」に見える在日━━
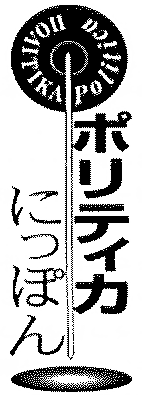
昨年の夏、大阪にでかけた折に猪飼野に立ち寄った。JR鶴橋駅からほど近く在日韓国・朝鮮人が多く住む「在日のメッカ」である。
キムチの店やチマ・チョゴリの店がずらりと並ぶ朝鮮市場を歩く。観音寺という韓国風の大きなお寺がある。「日本に来て60年もたつと朝鮮半島の父祖の地と縁遠くなりますからね」とかで、在日の人たちの納骨堂もある。
御幸森神社には仁徳天皇がここに住む百済人に会いに来た故事が伝わる。もちろんいまの猪飼野の在日はその子孫ではなく、植民地時代に平野川の掘削工事などに働きに来た人たちの子孫である。
長いかかわりなんですね、と焼き肉屋で在日の人たちと語りあう。「ワンコリア」、まず在日から心をひとつに、いつか祖国をひとつに、という彼らの思いを聞く。その後、拉致問題がこんな状況になるとは予想しなかった。
正月休みに映画「夜を賭けて」(金守珍監督)を見た。梁石日氏の原作で、いまの大阪公園にあった旧大阪造幣廠のそばのコリアン集落の物語である。暴力と純愛、欲望と悲惨、笑いと涙。すさまじいエネルギーの映画だ。
終戦前日の45年8月14日、「アジア最大の兵器工場」の大阪造幣廠が爆撃され廃虚となる。50年から53年の朝鮮戦争で日本は好景気の軌道に乗る。58年、清川虹子演ずるヨドギ婆さんが造幣廠跡から鉄屑を掘り出し大金を得た。それから毎夜、集落の人々が争って鉄屑を掘り出しに行くところから物語が始まる。
廃虚とはいえ、もともとは国有財産である。映画の主人公、山本太郎の演ずる金義夫ら鉄屑窃盗集団を警察は照明弾と警察犬で追い回す。彼らは西部劇のインディアンになぞらえて「アパッチ」と呼ばれた。当時の新聞をにぎわした実話である。
映画の1シーンの会話がそのころの在日を取り巻く政治状況を浮き彫りにする。
金村「刑務所送りになったら、長崎の大村収容所にまわされるちゅう噂や」
徳山「韓国に強制送還されるんやて。アメリカと組んだ軍事独裁の李承晩や。みんなアカにされて死刑らしい」
義夫「ここかて収容所や。塀がないだけの話や」
吉子「いっそ共和国いきたいわ。金日成様のもとでのびのび暮らしたい」
徳山「この8月には、共和国の偉いさんが日本から帰りたい者は熱烈に歓迎すると言うとるらしい」
少年「アポジ(父)。僕は共和国へ帰ります」
父「なんやと」
少年「金日成大学入ってゆくゆくは祖国統一のためにこの身をなげうちます」
父「ええ考えやがな、他のだれかにしてもらえ。家族がこれ以上離ればなれになるのは許さん」
金山「朝鮮戦争で男がようけ死んださかい、女がようけ余っとって、嫁さんよりどりみどりらしで」
金村「ほんまか。50前のわしでもええやろか」
日本の植民地から祖国の分断そして内戦。韓国は反共に覆われ、北朝鮮は幻想に包まれていた。それぞれの国に帰った人たちがいる。日本で生き抜いた人たちがいる。
昨秋、日本に帰国した拉致の5人の北朝鮮で生まれ育った子どもたち、横田めぐみさんの娘キム・ヘギョンさんの状況を懸命に想像するとき、そこには在日の人々を裏返したような境遇を感ずる。むろん理由も時代背景も違う要素も大きいけれども。
年末の「ワンコリアフェスティバル2002」のシンポジウムで姜尚中東大教授はこう言っていた。
「いま在日の意味を自分の肉声で語れる地平ができてきた。もう友とか敵とかいう対立関係でなく、ともに生きるべき存在となるべきだ」
北朝鮮は拉致問題を真剣誠実に解決せよ、核開発の瀬戸際政策はよせと言い続けるとともに、その先に北東アジアの平和像と人々の共生の理念を持っていたい。
猪飼野に住む旧知の日本人に電話すると、こう言った。「ここの在日の友だちは韓国の廬武鉉大統領誕生を喜んでますよ。戦争より平和をはっきり選んだ韓国の人々はすごいって」